
お墓は住宅・車に次ぐくらいの人生における高額商品になります。それだけに慎重に選びたいというのが消費者にとっての本音ですが、お墓の価格の中身は、けっこう複雑です。
お墓の価格についての参考記事
墓石の見積り価格が違う!素人が簡単にできるチェックポイントとは?
墓石の値段は希少性が左右する!150種を超える石の価格について
墓石使用率5%!素人にもわかりやすく御影石の原石価格の謎に迫る
お墓の価格に政治が介入?リスキーな御影石の相場について
あなたのお墓は価格重視!それとも品質?産地ごとの長所と短所を紹介!
墓石の相場を単純化、素人でもわかりやすく石材店を比較する方法とは?
建物条件付き土地ってご存知でしょうか?その土地を購入すると予め指定された施工会社(ハウスメーカーなど)で家を建てることを条件とした土地のことを言います。
実は、お墓にも同じような仕組みがあるんです。住宅だったら施工会社の名前を出して土地を販売しているので、わかりますが、霊園の場合には、表向きは消費者にはわかりません。
それが元でトラブルになることもよくあります。そんなお墓の値段の落とし穴になりがちな霊園・墓地の仕組みを説明していきます。
 お客様
お客様


[ad#co-1]
目次
民間霊園の知られざる落とし穴
一口に霊園・墓地と言っても様々な形態があり、4つの形態にわけられます。
霊園・墓地の4つの種類
- みなし墓地(戦前からあるような集落墓地)
- 公営墓地(各自治体が経営母体)
- 寺院墓地(寺院が管理する墓地)
- 民間霊園(宗教法人が事業主体)
霊園・墓地には、管理運営する団体が倒産をして、お墓の持ち主が露頭に迷ってしまわぬよう、永続性・公共性が求められる非営利団体でなければ、開発許可がおりなくなっています。
具体的には、
- 都道府県や市町村の自治体
- 第三セクター
- 寺院などの宗教法人
といった非営利団体でなければ、新たに霊園・墓地を開発できません。つまり、開発業者や石材店が営利目的で霊園・墓地を開発することはできないことになります。
ここが単純な土地の取引とは全然違うところで、住宅であれば、建物条件付き土地のように施工会社が土地を開発して住宅とセットで販売することも可能なのですが、同じように霊園・墓地を石材店が開発してお墓とセットで販売することはできないのです。



宗教法人の名義を借りて石材店が民間霊園を開発


最近の民間霊園は今までの墓地の概念が変わってきて、ガーデニングを施して華やかな空間を演出したり、コンセプトのハッキリしたところも多くなってきています。
これらの民間霊園は「〇〇メモリアル」「〇〇聖地霊園」といったオシャレな名前が付けられていますが、開発許可の取れる宗教法人が事業主体になって、名義を借りた石材店が実際に開発していることが多いです。
華やかで明るいイメージは、消費者の嗜好を捉えた民間らしい発想ですよね。気に入って購入される方も多いそうです。
[ad#co-2]
霊園開発には億単位の金額が必要になることも
霊園開発には多額の費用が掛かります。規模の大きい霊園だと簡単に億の金額になります。そのような場合、石材店1社で負担するのには、金額が大き過ぎるので、数社で開発資金を負担することがほとんどです。
見返りとして提供した資金に応じて、霊園の区画が各石材店に割り当てられます。石材店の商売はお墓を売ることなので、墓地区画とお墓はセットで売られることになります。
石材店は表に出てきませんが、けっきょくは『建物条件付き土地』と何ら変わらないということです。
でも、消費者の多くはそんなことを知りません。墓地を購入したらお墓もセットで付いている認識のない方が多いです。ここに消費者との認識の差が生まれます。
多くの消費者が指定石材店制度の存在を知らない!
このような民間霊園の開発に携わった石材店でしか、お墓を建てることのできない制度を、指定石材店制度と言います。
これは、寺院墓地でも同様で、名義を借りて、石材店が開発するケースもあり、同じように指定石材店制度を設けている場合があります。問題は、多くの消費者がこの隠れた仕組みを知らないということです。
霊園の場所が気に入って契約をしたら、建てられる石材店が決まっていた。なんて、実際に指定石材店制度に関するトラブルは後を絶ちません。
本来であれば、消費者に周知徹底しておくべき事柄です。ただし、表立って石材店が開発に携わったというとイメージも良くないですよね。
当然の理屈として、開発資金を回収して、それ以上の利益を上げることが目的のはずなので、消費者も警戒することが目に見えています。
オブラートに包んだままにした方が、事業主体である宗教法人にも開発をした石材店にとっても都合の良い場合が多いのです。






指定石材店制度の謎ルールとは?
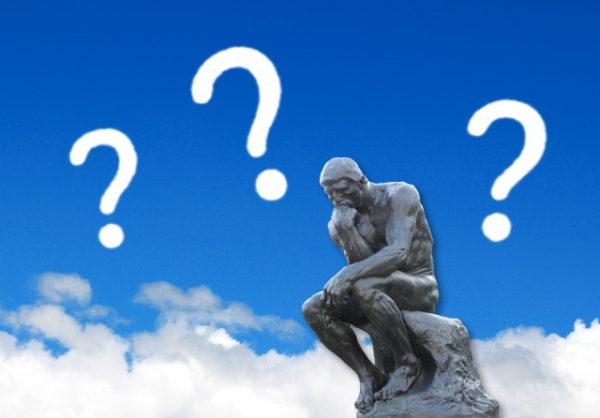
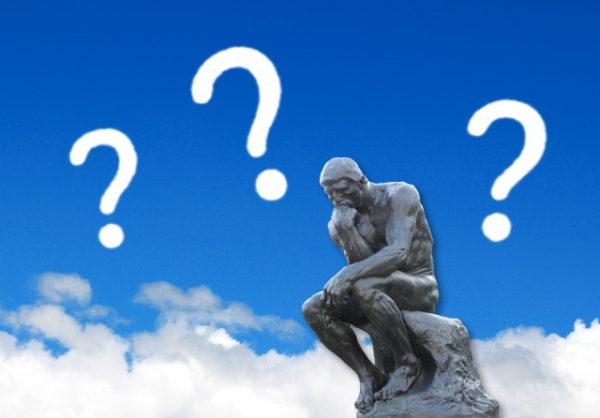
霊園・墓地の指定石材店制度には、その霊園に複数の石材店がいた場合に、霊園に訪問して最初に声を掛けた石材店が担当石材店になってしまうという謎ルールがあります。これは、石材店の名前の入った霊園の折り込みチラシを持って訪れても同様です。その折り込みチラシを発行した石材店の担当に自動的に決まってしまいます。
複数いる石材店同士で、ケンカにならないための棲み分けルールなのでしょうが、消費者にとっては、石材店を選択することができなくなる不明瞭極まりないシステムなのです。
お墓の値段にはどう反映される?
指定石材店制度だからお墓が高くなるのか?と言われると、そうでもないケースもあります。
多いのは、墓地+お墓のセット価格で販売される場合ですね。チラシで最初からうたってあったりして明瞭会計でわかりやすいです。お墓ばなれも言われ始めて、安くしないと消費者も中々買ってくれない時代になってきたんですね。
そうかと言えば、墓地の区画の値段を安くして興味を抱かせて、早く売れるようにしているケースもあります。儲けはお墓の価格に上乗せされます。
基本的に、区画を既に購入してしまって、お墓を建てることが決まっているお客さんにあまり安く販売することはしないでしょう。商売です。
[ad#co-3]
まとめ
『霊園・墓地の見学はちょっと待った!お墓の値段の落とし穴』ということで説明してきましたが、いかがでしたでしょうか?
民間霊園(寺院墓地)の指定石材店制度は、お墓の値段を不透明にしている場合があります。なるべくお墓の価格を抑えたいという方は、事前にその霊園の指定石材店を確認して慎重に選びましょう。
一方で、霊園・墓地の立地は大切な要因です。お墓を建てたのは良いけれど遠くてお参りもできないのではしょうがありません。その場合、少々高くてもプライスレスな部分を考慮して民間霊園を選ぶという選択肢もあります。
当選倍率が50倍とも言われる都営霊園の抽選を何度も落ちて、ずっと骨壺を家に置いている方もいらっしゃいます。それよりは早く民間霊園でもお墓を建ててしまった方が良いという考え方もあります。
参考図書

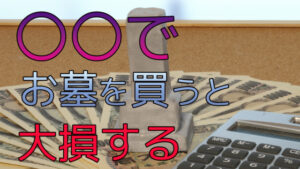
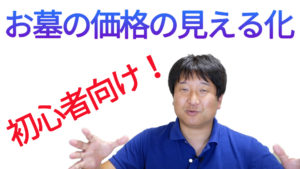






コメント