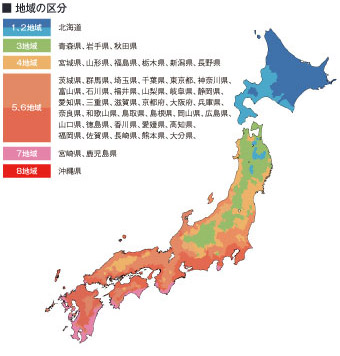
コンクリートは水分を含んでいるので、
固まる前に気温が低くなり寒くなると凍ります。
そうなると、きちんと硬化できなくて、
著しく品質が下がってしまいます。
ひどいと、表面からポロポロ崩れてしまうことがあるんですよ。
そうならない為にも、
冬季には、寒中コンクリートと言って、
特別に配慮されたコンクリートを打設する必要があります。
それでは、
【寒中コンクリート】冬季に強度が落ちる生コンの品質を高める方法!!
をお送りします。
目次
冬季には寒中コンクリートを
寒中コンクリートって何!?
寒中コンクリートとは、
コンクリート打ち込み後の養生期間中に、
コンクリートが凍結するおそれのある場合に、
施工されるコンクリートをいい、
生コンの強度、温度や初期養生方法に制約をもうけて、
凍結や強度増進に対して配慮するようになっている。これらに供給する 生コンについては、
次の事項に注意する必要がある。➀水・骨材の加熱は、
その装置・方法・温度等について、
責任技術者の承認を得なければならない。➁凍結防止のためには、
単位水量ができるだけ少なくなるように、
コンクリートの配合を定める。➂混和剤は購入者の承認を得たAE剤、
またはAE減水剤(促進形を用いることが多い)
を用いて、AEコンクリートとする。➃納入時の生コン温度の基準
(一般に土木用5~20℃)を確認する。➄セメントはいかなる方法でも加熱しないようにする。
⓺一般に、混合セメントのB種、
C種は低温の場合、
特に初期強度が小さいから不適当である。⓻凍結しているか、
または雪や氷の混入している骨材は、
そのままこれを用いないようにする。⓼骨材は直接、火で熱しないようにする。
⓽打ち込んだコンクリートの養生方法により、
コンクリート強度が異なるので、
生コンとして保証すべき強度(呼び強度)を確認する。引用元:全国生コンクリート工業組合連合会のwebサイトより
水は氷ると膨張して内部からコンクリートを破壊します。
初期凍害を受けたコンクリートは、
その後適切な養生を行っても強度を回復することはなく、
耐久性、水密性等が著しく劣るようになります。
また、5℃程度以下の低温度にさらされると、
凝結および硬化反応が相当遅れます。
早期に施工荷重を受ける構造物では、
ひび割れ、残留変形等の問題が生じやすくなります。
そうならないために、
色々と対策のしてあるコンクリートを、
寒中コンクリートと呼びます。
AEコンクリートはクッションの役目
寒中コンクリートには、AEコンクリート必須です。
水を減らして、滑らかにする役目を果たします。
AE剤は界面活性剤の一種であり、
コンクリート1m3中に数千億もの気泡を作り出します。
気泡が流動性を保ち、
単位水量を少なくできるので、
良くしまった密度と強度に優れたコンクリートをつくることができます。
また、水分は氷ると膨張しますが、
AE剤の気泡がクッションのように作用するため、
気泡に入り込んだ水が凍結して、
割れ等を起こす凍害に対しても耐性を持たせることができます。
基本的に、生コンをプラントに発注すると、
冬だろうが夏だろうが、
AE剤は混入されています。
AE剤は、水量を少なくして、
生コンをなめらかにするというAE剤の役目は、
年間を通してコンクリートの品質を上げるのに有効です。
自分で手練りで生コンを作る際には、
プラントに発注するよりも、
よほどコンクリートの凍害には、
気を付けた方が良いということです。
生コンの呼び強度を上げる
また、呼び強度の設定が必要になります。
寒中だと、寒くてコンクリートが硬化しずらくなり、
通常よりも強度が低いコンクリートになってしまいます。
なので、設計されているコンクリートの強度よりも、
実際に打設するコンクリートの強度
(呼び強度)を上げて補うのです。
例えば、設計強度21N/㎜2だったら、
29N/㎜2に強度を上げます。
強度の高いコンクリートの方が、
水和反応という硬化するための、
科学反応の速度が速く、
コンクリートの温度も早くあがります。
水和反応には熱が伴います。
これを温度補正と呼びます。
寒中コンクリートは気温との戦い!
寒中のコンクリート打設は非常に気を使います。
気温によって段取りするものが変わってくるので、
天気予報とにらめっこです。
平成25年省エネ基準の地域区分です。
数字が低いほど寒い地域になります。
都道府県のほとんどが5、6地域に収まっています。
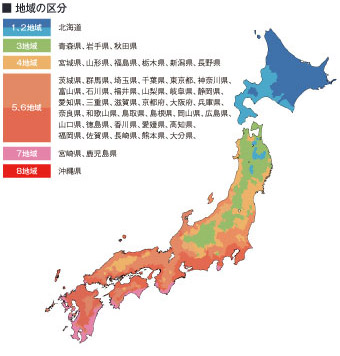
茨城県も5地域に分類されています。
その中でも気温に差があり、
海沿いは暖かく内陸に入るほど寒くなります。
比較的内陸である桜川市では雪が降っているのに、
海に近い水戸市では雨が降っている、
なんてことはよくあることです。
霜が降りる回数も全然違います。
それだけに特別な配慮が必要になるということですね。
[ad#co-3]まとめ
寒中コンクリートについてまとめて、
みましたがいかがでしたでしょうか?
寒中コンクリート対策としては、
最初の生コンの設定が非常に重要になってきます。
きちんと、生コンプラントと配合計画を相談するなりして、
冬季には下がりがちな生コンの品質を、
維持できるように設定しましょう。
また、最後になりましがた、
生コンの養生も大変重要なポイントになります。
生コンを打設したその日が勝負です。
一晩は、コンクリート温度を5℃以上に保ち、
さらに2日間は0℃以上に保つことが標準です。
そうすることによって、
冬季でも十分に品質の良いコンクリートを、
打設することができるのです。




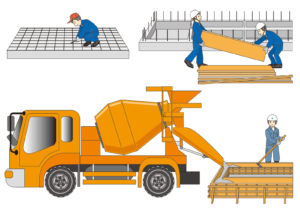



コメント