
カチカチに硬い石ですが、水を吸うのはご存知でしょうか?石には吸水率というのがあり、どのくらい水を吸うのか数字で表されているのです。
例えば、雨に濡れた石の色が変わっているのを見たことがありますでしょうか?和風の庭園で庭石が雨で塗れると色が変わり情緒ある風景になります。
これはもちろんお墓に使用する御影石でも同じで水を吸います。そして、一般的に水を吸う石は経年劣化が早くて良くないとされています。
今回のブログは吸水率が高いと風化が速いのは本当なのでしょうか?という話です。結論から申し上げますと、石は悠久の歴史の中で少しづつ風化していくもので人間の物差しで測るのはそもそも間違いということです。吸水率が高い本小松石のお墓が立派に建っています。
実際に急速に劣化が進んでいる墓石を見かけることがありますが、吸水率だけでなく複合的な理由が原因と思われるケースが多いです。
また、公称されている石種毎の吸水率がそもそも参考にしかならない数字だったりします。その辺りの吸水率のタブーについても迫ってみます。
[ad#co-1]
目次
お墓に使用する御影石は水を吸う!


墓石に使用する御影石は水を吸います。上の写真の切出水鉢の下の方の色が変わっていますが、これは水を吸っている状態だからです。水鉢の下の方は比較的水が残りやすくこのように吸っている状態にあることが多いです。
これ自体は、石が天然素材である証拠であり、なんら問題のあることではありません。



石がどれぐらい水を吸うのかわかりますか?
石がどれくらい水を吸うのかを数字で表したのが吸水率になります。数字が高いほど水を吸い、低いほど水を吸いにくくなります。
一般的に安山岩が水を吸いやすく、次いで先の切出水鉢の例でも出た花崗岩、黒御影石と呼ばれるような斑レイ岩は、吸水率が低くなります。
吸水率という罠
多くの石種では、吸水率が公称されています。私たち石屋もその数値を基に「この石は水を吸わない」「この石は水を吸う」といった判断をしています。だけれども、実はこの吸水率という数字は曖昧なものなのです。
例えば、中国産のG623という石があります。ネットをちょっと検索してみると2種類の物性データが出てきました。物性データとは吸水率も含んだ石の性質を示す数値です。
G623
- 見掛け比重 2.62t/㎡
- 吸水率 0.186%
- 圧縮強度 104.17N/m㎥
G623
- 見掛け比重 2.62t/㎡
- 吸水率 0.33%
- 圧縮強度 110.35N/m㎥
特に吸水率の部分を良く見て欲しいのですが、0.186%と0.33%とで数字に差があります。0.186%だと標準的な花崗岩の吸水率であり、0.33%だとけっこう水を吸う方になります。
これだけの差があると、一般消費者には別の石のように思えるかもしれません。だけど天然素材である石は、同じ石でも物性データがけっこう変わるのです。
吸水率は変わるし、当てにならない。


例えば、PCのスペックはCPU・メモリなどで性能を表すことができます。いわゆるスペックというやつですね。車にもスペックがあります。これで他社の同じクラスの車と比較することもできます。
それを石で置換えて考えると物性データが石におけるスペックのように思えるかもしれません。実際に石のスペックとして存在している面もあるのですが、気をつけなければならないのはあくまで参考値でしかないということです。PCのスペックとは全然違うのです。
石の吸水率は毎回変わる
私の勤めている羽黒石材工業㈱では、稲田石という花崗岩を採掘しています。それで毎年、物性データを調べるために試験をします。吸水率や圧縮強度を調べるのですが、これは公共事業などに利用される際に、性能を保証するために必要になります。
それはいくつかサンプルとなる石を抽出して行うのですが、全てのサンプルの数字が異なります。その平均値を物性データとして扱います。つまり何が言いたいかと申しますと、同じ稲田石でも同じ性能が出るわけではなく個体差があります。考えれば当たり前で天然のものなのでばらつきがあるはずなのです。
公称されているその石を表す物性データは、ある時期のある場所にあった石の平均値を表したに過ぎません。たまたま低い吸水率が出た可能性もあります。いずれにしても個体差があるので参考程度にしかならず、吸水率を目安とすることが意味をなさなくなってきます。
吸水率神話に疑問符
そうは言っても吸水率神話は強いです。あえて吸水率神話と言っていますが、石屋さんもけっこう「この石は吸水率が低いのでお勧めです!」という言葉を口にされます。確かに黒御影石に代表される斑レイ岩は吸水率が低いのは間違いないのですが、こと花崗岩においては疑問符がつきます。
そして、最近の消費者はとても勉強熱心です。私に相談される方にも吸水率を重要視される人が多くいらっしゃいます。だけども私は「参考程度に留めた方がいいですよ。」といつも言っています。
確かに吸水率で比較すると単純ですし、わかりやすいです。石のカタログを見ればどんな石種でも大抵は物性データが載っていますし、PCのスペックを比較するかのように石を比較することができます。ここに石屋さんも消費者ものっかっている感じがしています。
吸水率が高いと経年劣化が早い?
ところで、なんでこんなにも吸水率神話が取りざたされているかと申しますと、吸水率が高い石は経年劣化が早いという話があるからです。これは確かにそうです。
例えば、同じ真壁小目石でも吸水率の高い原石は、灯篭などの制作に使われます。これは灯篭はコケが生えて味わいを増した方が価値がでるからで、わざと吸水しやすい、いわばちょっとボロい石を利用します。もちろん墓石に使用されるような一級品と比較すると風化の速度は速いでしょう。


本小松石は吸水率が高いけど、古いお墓でもまだまだ健全なものが多いです。昭和47年に亡くなられた志賀直哉のお墓はまだまだしっかりしていますね。昭和2年に亡くなった芥川龍之介のお墓も本小松石ですが、文字のところがちょっと欠けただけでまだまだ問題ありません。


100年経った稲田石のお墓でも石肌がザラザラしていますが、刻んだ文字がまだまだハッキリと確認できます。
中国産墓石は、特に吸水率の数値の幅が広いという話を聞いたことがあります。それは、原石からの製品化率が高いからで、少し難のある原石でも使用してしまうからです。それでも急速な風化にはつながらないと思います。
石の風化の速度は、人間が心配するほどのことじゃないかもしれません。風化はしますが、よっぽど人間の老化の方が早いですから(笑)
人為的な急速な経年劣化には要注意!


ただし、自然な風化じゃなくて外部からの影響で一気に劣化が進む場合があります。それらについては以前記事でも書いています。
サブフロレッセンスは、石を内部から破壊します。


以前に茨城県石材組合連合会にて2400区画の墓地を調査して経年劣化状況を調べています。けっこう国産墓石と中国産墓石で劣化状況に差があるのが興味深いところです。


中国産墓石の劣化が早いのは、磨きの工程が早くて、さらにこういった薬品が使用されていることも原因の一旦かもしれません。


中国産墓石は、価格的なメリットが大きいですが、その分生産性を高めるために吸水率が高めの石も利用しがちです。これは単純に良い悪いの問題ではなく安価な墓石を求めるニーズに応えてのことですが、複合的に悪条件が重なると経年劣化の早いお墓になる可能性があります。
吸水率うんぬんは置いといて自然な風化ならいいんじゃないかなぁ
人は年をとります。お墓も年をとります。私は40才を越え、小じわが増え、肌も衰えてきました。健康診断をすると悪い数値もチラホラ見られます。お墓も同じようにゆっくりですが年をとります。
だけど、それがいいと思えるようになりました。だから石という素材がお墓に利用されているんです。私たちと一緒に年をとります。それは亡くなられた故人、そしてご先祖様と私たちが共に歩んでいるという証拠でもあり。時が風化という形で石に刻みます。
とは言え、10年20年では、今どきのお墓は目立って風化しません。50年でもまだまだでしょう。なのであまり心配するだけ損のような気がしています。気になるのならコーティングをしてみるのもいいかもしれません。アンチエイジングですね。
お墓を購入される方の多くは、吸水率を心配され、そして私たち石屋も吸水率を誇張して伝えることもあり、なんだか吸水率に踊らされていると感じることがあります。そんなに当てになる数字じゃないし、ほどほどに受け止めた方がよろしいと感じます。
[ad#co-3]まとめ
とういことでお墓に使用する石の吸水率について説明してきました。お墓に使用する石種を検討する上で吸水率という言葉を良く聴きますが、あくまで参考数値であって当てにならないということをご理解いただければと思います。
だけども他に石にとって目安となるスペックがないのも事実です。だから余計に吸水率が独り歩きしてしまう傾向があるのでしょうね。
そんな中で私は吸水率神話を否定します。いや否定なんて大それたものでもないけど、あんまり気にする必要はないと感じます。石は人間の生きる期間とは比較にならない悠久の時に身を置いています。唯一心配するのは人為的な経年劣化だけです。そこだけは気をつけたいものだと思うのです。
1級お墓ディレクターの「なかの」はこんな人ですよ。
自己紹介・プロフィール
こんな会社に勤めていますよ。
羽黒石材工業株式会社
お墓についてご相談したい方はこちらにどうぞ。
お問い合わせ
いろいろとご相談したい方、@LINEもやってます。
[ad#line]
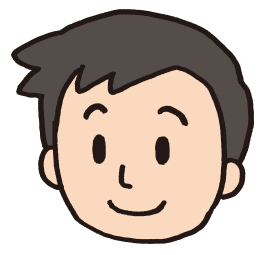






コメント